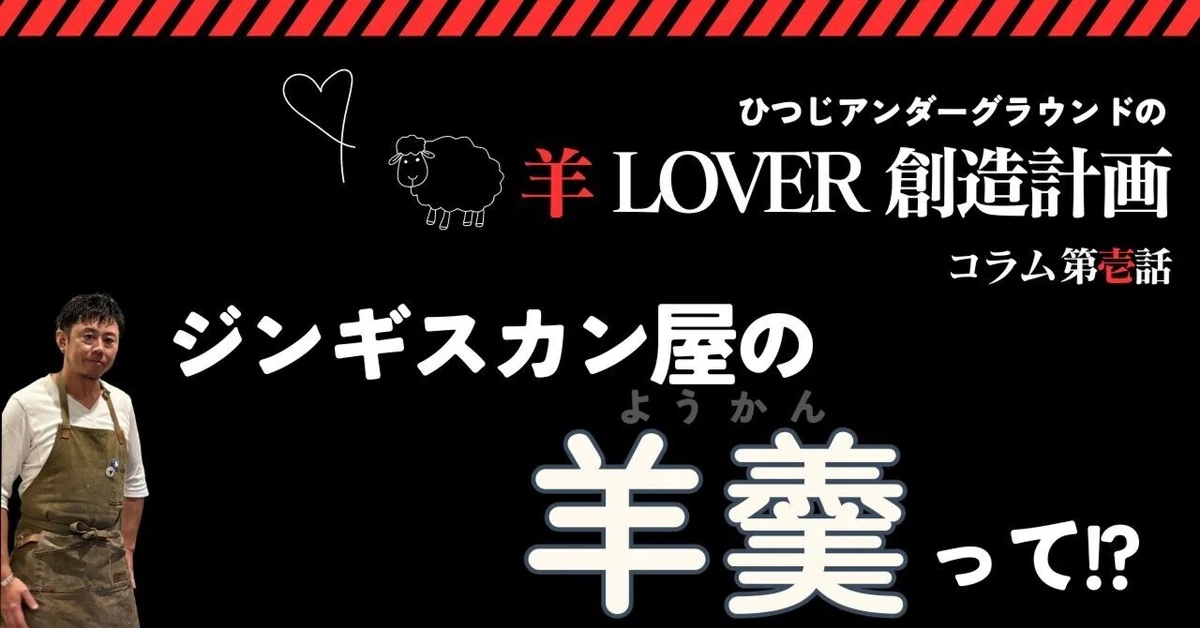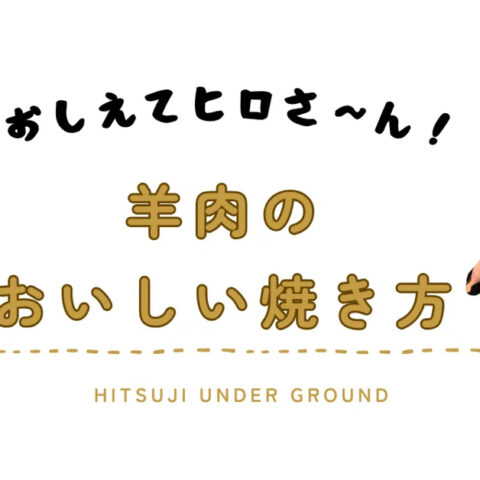【コラム第壱話】
ジンギスカン屋の羊羹って!?
今月はいつもと少し趣向を変えて、羊にまつわるあれこれを気軽にお話しするコラムをお届けしようと思います。
私たちが掲げる 羊LOVER創造計画 は、ご存じエヴァンゲリオンのオマージュ的なタイトル。…ということでトップの画像もなんとなくエヴァ風味にしてみました(笑)
さてさて、初回のテーマは 「羊羹」 についてです!
お通しに「羊羹」?
ひつじアンダーグラウンドのある日のお通し。
「羊羹です」

ジンギスカンを食べに来たにもかかわらず、テーブルに出されたのは羊羹。突然の変化球に、多くのお客さまは驚かれます。
ところが当店としては最初のつかみは完璧。
「実はですねぇ・・・・」(ニヤリ)
と、ここから羊トークを繰り広げます。これが羊LOVERの普及活動に日々勤しむ当店の日常の一コマです(笑)
羊羹に「羊」という漢字が入っているワケ
和菓子の定番、羊羹。漢字でかくと「羊」という漢字が入っていますよね。
羊羹という言葉は、「羊」と「羹」という漢字で成り立っています。あつものとは、汁物/スープという意味。実は本来の羊羹とは、羊の肉を使った中国のスープのこと。これが冷えることで羊肉のゼラチン質が固まって、煮こごりのような形になったんですね。
日本に羊羹が伝わったのは鎌倉から室町時代までさかのぼります。中国に留学した禅僧によって持ち込まれたとされていますが、禅僧は肉食が禁じられていました。そこで代わりに植物性の材料を使って羊羹を再現したとされています。時代とともに甘みが加わり、400年以上前には現在の和菓子の羊羹の形が完成したのだとか。

山椒がふわりと香り、口に含むと旨みがじゅわっととろけてスープ(羹)に戻るような感じがします。めちゃくちゃおいしい!しかも、羊羹の歴史を知るとさらに味わい深く感じるんですよね。
ところで、人間は羊と1万年前から共に暮らしてきたという説もあるほど、羊は世界的に長い歴史を持つ生き物なんです。その一方で、日本での羊肉食の歴史はまだわずか100年ほど。だからこそ、日本人にとっては羊=ジンギスカンという印象が強いかもしれません。
「羊との付き合いが長い世界各地には羊の伝統料理がたくさんあるんです。月替わりで世界の羊料理をお通しとしてお出しすることで、羊の魅力や歴史を知ってもらえたらと考えています」と店長の森保が話すように、中国生まれの羊の水餃子「餃子湯」や、ギリシャ発祥のナスと羊挽肉のグラタン風「ムサカ」など、お通しが好評だったことからグランドメニューに仲間入りした料理も。
ジンギスカン以外にも、いろいろな世界の羊料理をお試しいただけると嬉しいです。もちろん、羊トークもぜひご一緒に。